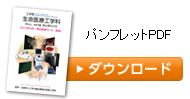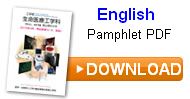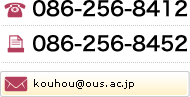「病院実習まで1年!」の風景
2017.07.21
 |
| 実習内容に関連した知識などについてレクチャー(指導)を受けています。「コレ、授業でやってるハズだけど覚えてるかな~?」と聞かれギクりとするのも勉強するひとつのキッカケに。 |
 |
|
先輩にアドバイスやヒントをもらいながらトライ。色々知ってる先輩はありがたい存在です。 |
 |
| 先輩に見守られながら次の実習項目の準備。準備するにも、実習内容を前もってよーく勉強しておく必要があります。 |
 |
| こんな感じかな、と自分でやってみる。そうそう、自分でやってみることこそが実習のポイントです。 |
 |
| 機器を分解して構造や仕組みを確認。病院ではたらくエンジニアを目指してやっている、という雰囲気が漂います。 |
3年生になると、臨床工学コースの学生を主とした医療機器を使っての実習があります。翌年の病院での実習を控え、専用の施設で1年間をかけてみっちりと鍛えられます。他の授業もありますが、臨床工学技士を目指している学生にとっては、この実習が、もっとも大変でもっともやり甲斐があり、自分の目指している世界をもっとも感じられる授業でしょう。
この日は人工透析器を使った実習。人工透析器は、人間の腎臓に代わって血液中から老廃物を除去する「血液浄化装置」の一種で、臨床工学技士が取り扱う主要な医療機器のひとつです。チューブを人間の血管に接続し、装置に血液を循環させる仕組みですが,接続の際にチューブ内に気泡が入ってしまうと,気泡が毛細血管を塞いでしまう「空気塞栓(くうきそくせん)」という状態になって血液が流れなくなる恐れがでてきます。空気塞栓が起こると、毛細血管を流れる血液から酸素と栄養を得ていた組織が永遠に損傷してしまう危険がでてきます。ですので、気泡がなるべく入らないように,入ってしまったらその気泡をしっかりと除去するように注意する必要があります。
チューブを接続する作業ひとつでも様々なことに注意しないといけない、そのことを体感しながら色々と身に付けていきます。