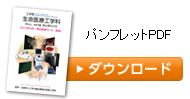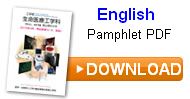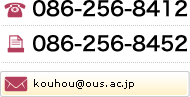卒業への最後の関門、卒研発表会(2月6日開催)
2017.02.10
 |
| 発表のときの様子。これだけ多くの人の前で話すのは初めての学生が多く、前もって練習していても緊張が高まります。 |
 |
| 発表が終わったら質疑応答、つまり質問タイムです。教員からの質問や指摘に答えなくてはいけません。発表自体は前もって準備できますが、質問はどんなものが出て来るかわからないため、多少の予想はするにしても、基本的には、いわゆるアドリブで臨むことになります。どう答えるかによって「自分の研究をどれだけ本当に理解しているか」が明らかになってしまうため、ある意味、発表そのものより緊張する時間帯でもあります。 |
 |
| 発表前の人たち。発表内容の最終確認をしたり、ブツブツとしゃべる練習をしたりしているところですが、緊張している様子が伝わります。 |
 |
| 発表後の人たち。「もう終わったもんねー」とばかりに笑顔が弾けます。その段階もすでに終わって、気が抜けたような表情になる人もいます。 |
 |
|
司会進行は後輩たちが務めます。先輩たちが緊張の時を過ごす様子を間近で見て、1年後の自分の姿に重ね合わせ、これから自分がしなくてはいけないことに思いを馳せたりします。武者震いしている人もいるかも知れません。 |
4年生による卒業研究発表会が行われました。
長い時間をかけてやってきた卒業研究の成果をこの発表会で報告し、学科全教員によって「合格に値(あたい)する」という評価を受けることによって、やっと卒業にたどり着くことができます。まさに「卒業への最後の関門」と言えます。
<卒業研究>
理科系の学生であれば、たいていの大学・学部・学科で課せられ、大学での勉学の集大成として位置付けられています。学生には、所属している研究室の教員の指導のもと、それまで授業等で学んできたことを活かし、新たに必要になった知識やスキル(何かを実施するためのワザ、腕)などを身に付け、そしてひとつの研究を成果としてまとめ上げることが求められます。
「何かを知っている」「何かができる」ということだけでなく、「何をしようとする研究なのか」「研究の結果わかったことは何か」といったことを、自分で考えたり他人に理解できるように説明したりすることが求められます。そういうわけで、研究活動を通して実に様々な力が鍛えられます。
もちろん大変ではありますが、人生の中でこういったトレーニングを受けるチャンスというのは実は非常に少なく、「卒業研究」は大学に来た醍醐味とも言える科目です。