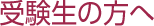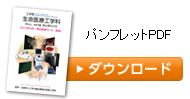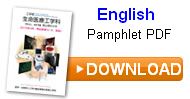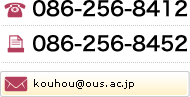出張講義
生命医療工学科のことをもっと知って欲しい!
私たちは学外に向けて、出張講義を行っています。
2018年度は以下に示す多彩な出張講義を企画致しました。
出張講義のお申込みは,本学入試広報部(TEL.086-256-8412)にご連絡ください。
今年度の出張講義一覧
医療機器と情報処理技術 教授 木原 朝彦 (生体情報工学研究室)
医療の現場では様々な装置がつかわれていますが、そこには最新の情報処理技術が使われています。 この講義では、医療機器の中から画像診断装置に焦点を当て、そこで使われている情報処理技術について分かりやすく解説します。
恐竜のバイオメカニクス 教授 内貴 猛 (バイオメカニクス研究室)
太古の昔に地球を支配していたと思われている恐竜は、中には体重100トンにも達する巨大な恐竜がいたことが知られています。そんな恐竜を現在の地球によみがえらせたらどうなるだろうと考えたことはないでしょうか。でも、生体工学の立場から考えると現在の地球では巨大な恐竜は自分の体重を支えることができないのです。そのような話からはじめ、恐竜絶滅のなぞを考え、太古の地球に思いをはせてみたいと思います。
あなたの髪の毛で健康状態がわかる?? 教授 猶原 順 (人間環境科学研究室)
分析機器の進歩により、髪の毛が1本あれば、健康状態が分かります。髪の毛は、あなたの健康状態や生活環境や食事の内容の影響を受け、必須元素や有害元素の種類や濃度がかわってきます。将来的にはガンや生活習慣病の検査に使えるかもしれません。これらの内容について紹介します。
医療に関わるバイオテクノロジー 教授 八田 貴 (遺伝子・分子生物学研究室)
バイオテクノロジーは、鉱工業、農業、などに使われています。近年では、医療の分野でバイオテクノロジーが抗生物質・診断薬・遺伝子診断など多くの場合に役立っています。 遺伝子診断では、イエローストーン国立公園で採取された微生物の酵素が使用されています。血液検査も微生物の酵素が使われています。最近では、iPSという万能細胞を使って臓器移植に向けた取り組みもされ始めています。
アポトーシスをめぐる酵素カスケードと細胞内シグナル伝達 教授 松木 範明 (医工学研究室)
細胞死は,受動的な壊死と能動的なプログラム細胞死に大別される。プログラム細胞死の代表であるアポトーシスは,組織発生や様々な病気の発症,進展に強く関与していることが知られている。講義では,アポトーシスに至る中心的な経路であるカスパーゼの活性化を題材に,細胞における酵素カスケードのしくみとともに,細胞内情報伝達機構の複雑なネットワーク(cAMP, IP3, PKC, Ca)についても解説する。
医学と工学の融合 准教授 小畑 秀明 (生体情報工学研究室)
病院で使用される医療機器は難しい仕組みで動く複雑な機械と思っている人もいるかもしれませんが、実際はとても単純な原理で簡単な構造をしたものがほとんどです。本講義では身近な医療機器から手術室で用いられるような命を守るための医療機器までの原理・仕組みについて解説します。また実際に医療現場で活躍する命を守るエンジニア「臨床工学技士」の仕事についても説明します。
医学の歴史と現代医療 准教授 小畑 秀明 (生体情報工学研究室)
医学の歴史は科学・工学の歴史でもあります。医学の歴史を見直しながら、科学とどう関連しながら医学が進歩してきたかについて解説します。また、現在の命の最先端の現場における医療と医療機器についても解説します。
超音波の医療応用 講師 松宮 潔 (医工学研究室)
音波の一種である超音波は,古くは敵の艦船(潜水艦など)の位置を知るための技術開発の一端として研究されてきました.医療応用の歴史も比較的長く,多くの場面で利用されています.たとえば超音波画像診断装置などはその代表格です.この講義では,超音波の性質をおさらいしつつ,どのような形で医療応用されているかを,原理も交えて解説します.
電磁波の医療応用 講師 松宮 潔 (医工学研究室)
電気,光,電波,レーザ,X線といった名称のものはすべて電磁波の一種です.電磁波の医療応用は多岐にわたっています.「電磁波とはどのようなものか」という話から始め,電気メス,マイクロ波ラジオ波治療器,レーザ治療器,X線CTなどについて,簡単な原理説明を交えながら解説します.
日本での不妊治療の現在 准教授 松浦 宏治 (マイクロ・ナノ生理学研究室)
1970年代後半から始まったヒト体外受精は現在、不妊治療には欠かせない技術となっています。この数十年間で日本においても不妊治療クリニックの数が増加し、不妊治療は身近な医療になってきました。現在日本で行われている不妊治療に関する治療技術と医療チームが抱えている課題などについて説明します。
医療に関わるナノテクノロジー 准教授 松浦 宏治 (マイクロ・ナノ生理学研究室)
2000年代初めからアメリカをはじめ各国で進められてきた「ナノテクノロジー」によって、さまざまな非常に小さい材料が生み出されてきました。バイオテクノロジーとの融合によって、農業・医療分野への応用開発も行われています。具体的には、トランジスタの小型化・高性能化、水質浄化膜の機能向上、がん細胞標的薬剤、細胞・臓器イメージング技術への展開が図られており、将来の医療が変わる可能性について紹介します。
多能性幹細胞と再生医療 准教授 神吉 けい太 (再生医療工学研究室)
病気やケガにより失われた体の機能を、細胞の力や組織の再生能力を使って回復させる医療が再生医療です。現在、体のどの細胞にも変化できる「万能細胞」を使った医療が実現しつつあります。ES細胞、iPS細胞などの多能性幹細胞と、それらを利用した再生医療の話題についてお話しします。
薬として活躍するタンパク質 准教授 二見 翠 (生体材料工学研究室)
タンパク質といえば肉や豆腐のような食べ物に含まれる三大栄養素の一つというイメージが頭の中に浮かぶのかもしれません。ところが、タンパク質は医薬品として欠かせないものになりつつあり、いまや世界の大型医薬品売上ランキングTOP10のうちの半分がタンパク質医薬品です。講義ではこれらタンパク質医薬品について具体的な病気の説明や薬の作用機構を交えながら紹介したいと思います。
工学部でなぜ生命科学を学ぶのか 准教授 二見 翠 (生体材料工学研究室)
「工学部で生命科学を勉強する」というのは、高校生の皆さんにとってその先何に繋がるのか、パッと頭に思い描きにくいのではないでしょうか。生物・生命に関する知見が産業にどのように活用されているのか、医薬品産業などを例に挙げ、紹介したいと思います。